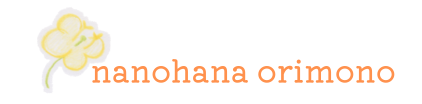我が家から車で20分ほどの場所に、宍塚大池を囲む広大な里山が広がっています。10年ほど前、幼稚園児だった娘と自然観察会に参加したことがきっかけで、母娘の里山通いが始まりました。
娘は、大好きなイモムシ探しから始まり、キノコ観察会で大きな「アカヤマドリ」を見つけてからはすっかりキノコの虜に。
四季を通して親子で里山を楽しむ日々。里山に携わる方々から、虫のこと、植物のこと、山菜、木の剪定、里山の歴史など、たくさんのことを学んでいます。使われなくなった里山をボランティアというかたちで保全するスタッフ方には、感謝しかありません。
生活が便利になるにつれて、使われなくなった里山ですが、利用すること=保全だと感じています。里山って、食べ物の宝庫なんです。春は、フキノトウから始まり、タケノコ、セリ、ミツバ。夏が近づいてくると、桑の実やモミジイチゴ、雨が多いとキクラゲもたくさん。放置状態だった梅の木も、剪定を始めたら少し元気になって、たくさんの実をつけてくれます。秋になるとアケビ、ムカゴ、クルミ、柿に栗、寒くなってきたらヒラタケやエノキのシーズン。収穫ほど楽しいものはありません!
そして、里山は染料の宝庫でもあります。剪定した梅の枝、ニホンアカネの根、クサギの実やクルミの未熟な実、ヌルデの五倍子など。ふと、里山と機織りって繋がっているんだ!?と気が付いて「私がやりかったことはこれだ!」と嬉しくなりました。
里山には、桑の木もあります。蚕を育て、繭から真綿を作り、糸をつむぐ。里山の植物で糸を染めて、機を織る。一昔前までは、自然に営まれてきた流れに気付くのに、だいぶ時間がかかりました。やっと見つけた「やりたいこと」に向かって、進んでいきたいと思います。
nanohana orimono 立ち上げ
自分の名前の由来から、nanohana orimonoに決定。
ローマ字表記にすると、丸っぽくてかわいらしいのも気に入っています。
私は、形から入るタイプ。
名前が決まったら、次はロゴ!
季節はちょうど春。菜の花を摘んできて、お絵描き。
ロゴができたら、名刺、ホームページ、ネットショップ、YouTube。。。
眠っていた一眼レフカメラも取り出してきて、写真の練習。。。
ちょうどコロナ禍で時間があったのもあり、着々と準備。
さて次は、何を織る?
手つむぎ糸を肌で感じてほしい!
ということで、ストールに決定。
使ってみた感想は、ふわっと軽くて温かい。
首に巻いても、重さを感じないので疲れません。
ちょっと汗ばむ季節でも、速乾性があるのでサラッとベタつくことなく心地よし。
使い込むほどに、糊が抜けて柔らかくなる結城紬。
長く愛用いただくことで、変化を楽しんでいただけるストールなのですが。
販売のノウハウがないので、必要としてくれる方になかなか巡り会えない。。。
まあ、焦っても仕方ないので、気長に待つことに。
さて、結城紬は、分業制。
私は、織りしかできないので、織りまでの下ごしらえは「機屋」さんにお願いします。
ある時、「手つむぎ糸が手に入りにくいから、ちょっと時間かかるよ」と言われて。
うーん。産地の状況を考えると、手つむぎ糸が減少していくことは確実。
糸とりといえば、縁側でおばあちゃんが日向ぼっこしながら糸をつむぐイメージですが。
時代は変わり、そんな光景は昔話の世界。
糸とりって、真綿から糸を引き出してはつむいでいく、なんとも地味な仕事なのですが、
無になれる時間でもあり、ラジオを聴きながらリラックスできる時間でもあり。
ストレスフルな時代の息抜きにぴったり🎶
そうよ!糸がないなら、取ればいいじゃない?という発想で糸とりから始めることにしました。
手つむぎ糸の単位は、「おぼけ」と呼ばれる桶一杯分=1ぼっち(約100g)で取引されます。
1反の着物に必要な糸量は約7ぼっち。
ちなみに、私が1ぼっちの糸とりにかかった時間は約70時間。
1ぼっち(70時間)×7=1反分の糸とり時間(490時間)
こりゃ大変だわ。
でも、急ぐ必要もないし。
ちょっと立ち止まって考える時間もできて、ちょうど良いです。
糸をつむぎながら、思うこと。
蚕を育て、真綿を作り、糸をつむいで、機を織り、着物に仕立てる。
急ぎ過ぎてる世の中に、緩やかなブレーキをかけられるのでは?と思う日々。
なにも、ぜーんぶ、昔ながらの手仕事に戻るわけではなく。
機織りでもいいし、裁縫でも、編み物でも。
衣服にこだわらず、DIYでも、家庭菜園でも。
衣食住って、もともとは、暮らしの中にあったのだから。。。
お金で、なんでも買える時代に変わったけど、
自分の手を使い、生きていくためのなにかを作る時間って大切だと感じています。
織り子としての日々
2010年、茨城県の後継者育成研修を受講。
1年間の研修期間で、帯1本、反物2反の下拵えから織りをしっかりと学び、
研修後は機屋さんに所属し結城紬の機織りに従事するという内容。
研修生4名のうち、自宅から通っているのは私のみ。
3人は遠方からの参加者で、アパートを借りて参加。
「気合いが違うなー」と心から尊敬しておりました。
初心者4名の下拵えは、笑っちゃうほど時間がかかります。
まずは「機結び」の練習から。
手つむぎ糸は、切れるのが当たり前。
初心者には、結ぶのも一苦労。
しかも、上手く結べず、すぐに解ける!
とにかく、大変な作業が続くのですが、明るいメンバーに囲まれて、
いつも笑って作業していた記憶があります。
さて、1年間の研修を経て、機屋さんに所属。
その当時の機屋さんの状況は、
下拵えと外回り、の他に、なんでも担当する社長。
機織りと下ごしらえも担当する奥さん。
通いの織り子さんが2名。
自宅で織っている織り子さんが数名。
そこに、私も含め新人2名が追加。
常に機織りの音が響いて、賑やかでした。
週6日、手際よく細かい絣の反物を織っていくベテランの先輩の横で、
亀のようなノロノロペースの私。
お昼とお茶の時間は、たっぷりとおしゃべりタイム。
産地の昔話や現状、織り子になったきっかけや、織り賃の話。
織り賃は減少傾向、反物検査は年々厳しくなる、生産反数は減る一方。。。
暗い話題が多いのですが、みなさん底抜けに明るい!
織りが好き、おしゃべりが好き、お出かけが好き。
月一回のランチ会、年一回の遠くへお出かけ。
10年以上、現在まで続いている、織り子仲間の恒例行事です。
通っていたのは1年ですが、とても充実した時間でした。
2年目からは、自宅にて機織り。
織りはじめは、一日に何尺織る!と目標を決めて、
コンスタントに織っていたのですが。。。
妊娠、そして、育児しながらの機織り。
思うように進まず。
安定した現金収入が必要かも?と。
パートタイムのお仕事を掛け持ちすると、
さらに、織りのペースが落ちてしまう。
そして、コロナ禍。
結城紬の生産反数はさらに減少。
今後の機織り生活、どうしよう?
と考えはじめた時に思いついたのが。
「注文がないなら、自分で立ち上げてみるか?」
こんな流れで、nanohana orimono を立ち上げました。
結城紬との出会い
機織りをしています!と自己紹介すると返ってくることば。
「手先が器用なんですねー」
→いえいえ。全く不器用。幼稚園の時、鶴が折れなくて心配されるレベル。機織りをはじめて気づいたことは、手先は使えば使うほど、器用になっていく。
「着物に興味がおありなんですねー」
→着物の記憶といえば、成人式の写真用に親が選んだ着物くらい。機を織る者として着物くらい着れないと!と、着付け教室に通ったきっかけで、少しずつ着物を着る機会が増えています。
「伝統工芸がお好きなんですねー」
→無縁の世界でしたが、人の手で丁寧に作られているものに引き込まれていく日々。
では、なぜ、機織りをしているか?というと。
きっかけは、社会人学生時代に受講した湯澤規子先生の「農村社会学」。
先生はライフヒストリーを用いて結城紬の産地を研究。日々の暮らしの中に機織りの仕事があったという講義内容に共感。これから、どんな働き方をしようかなあ?と悩んでいた時期でもあり、直感的に「私のやりたいことはこれだ!」と思い立ちました。
女性の社会進出、男性と同じように働く時代という教えに、疑問を感じていたので!
家事をしながら、
子育てしながら、
親の介護をしながら、
ライフスタイルに合わせた仕事ができるのでは?と気持ちがふわっと明るくなったことを思い出します。
私の目指している仕事はこれかも!?と機織りの世界に飛び込みました。
結城紬下ごしらえ研修会4日目 2024/12/13
4日目は機巻きです。
経糸を伸ばして巻いていくので、長さが必要。
経糸を固定する道具は建物の外に設置。
扉は開けっぱなし状態。。。寒い。。。

みんなで糸をさばきながら巻いていくのですが、経糸が切れて切れて進まない。
経糸をさばくにもコツがあり、社長のスピードについていけない💦
そんな時に社長がつぶやいたお言葉
「仕事だから、でれでれやってもしょうがない。」
確かに。。。効率よく進めなければ。。。

糸をさばいては巻き。
切れた糸は、糸道を見ながら相手を探し、見つけて、繋ぐ。
切れてはつなぎの繰り返し作業。
根気のいる作業です。
社長のお家では、社長と奥さんのお二人で機巻きするのですが、
時間がかかればかかるほど、会話がなくなるね。とお話してました。
お二人のお気持ち、納得できます。
さて、研修は4日で終了の予定でしたが。。。
機巻きの途中で終わってしまいました!
せっかくなので、引き続きやりましょう〜となり。
1/4.1/5に追加で研修会をおこないます。
また、みなさんにお会いできるのが楽しみです。
結城紬下ごしらえ研修会3日目 2024/12/12
3日目は、Oさんの生徒さんと結城紬の織り子経験者のMさんも加わり、
大人数、賑やかな講習会となりました。
まずは、整経が終わった経糸の糊付け作業。
小麦粉の濃度18%の液につけるのですが。
小麦粉の種類、ダマにならないような溶き方、お湯の温度、などなど。
たくさんのポイントがありました。
社長のお言葉
「経糸の糊付けが上手くいけば、下ごしらえは成功」
と言われるくらい、糊付けがポイントとのお話。
この後に続く、機巻きや機織りも、経糸の具合で作業のやりやすさが格段に違います。
糊付け後は、経糸を吊って、どんどん乾いていく糸を手早くさばきます。
人手があるほど、効率が良いです。
乾燥しているので、あっという間に乾きます。
その後は、筬通しの準備。
綾の部分を、一つ一つほぐします。
綾を崩さないよう、丁寧に作業。
指を使う作業が、とても多いです。。。
やっと、筬通し。
670箇所に、上下の経糸2本を通していきます。
これが、見えない見えない。
「から」と呼ばれる、筬目を飛ばして通さないように。
「4つ入れ」と呼ばれる、一つの筬目にダブって通すことがないように。
細心の注意を払って、通していきます。
3日目は筬通しで終了。
慣れない作業で体がカチコチ。。。
結城紬下ごしらえ研修会2日目 2024/12/10
昨日に引き続き、管巻き。
やっと、午前中に終わり、午後から整経スタート。
22本の管を設置し、整経台に延べていきますが。
まずは、縞のパターン決め。

筬目670(反物横幅の糸の本数)÷22=30 で、この22本の縞模様が30並びます。
下ごしらえは、計算が必須。
まずは、社長の見本からはじまり、メンバー順々に延べました。
人が変わると、延べ具合も変わる。。。
社長はゆったり長め、研修生はキツキツで短め。
2日目の社長のお言葉
「整経は、はじめの人に合わせるべき」
初心者には、難しいですねー。
1延べごとに、綾をとります。
どんな縞になるのか、楽しみ🎶
結城紬下ごしらえ研修会1日目 2024/12/9
結城市、伝統工芸コミュニティーセンターでおこなわれた、
結城紬の下ごしらえ研修会に参加。
参加申し込みなしの研修会、どんなメンバーが集まるのから?とドキドキでした。
参加メンバーは3名。
同じ機屋さんの後輩S氏と初めましてのOさんと私。
なんと、Oさんは30年前に住み込みの織り子として結城紬を織っていた経験者で、
その後、東京で機織り教室を開いている大先輩。
結城紬の織り子さんは、機屋さんに所属しているので、
他の機屋さんの方と接することが、少ないです。
なので、境遇が違う織り子さんとの出会いは嬉しいです🎶
さてさて、1日目の研修は、
「整経用の経糸糊付け」と「管巻き」
経糸の必要量は、
着尺の長さ38.4尺×筬目670箇所×2(上糸下糸)
というわけで、糊付けした糸をひたすら管巻き
糸の太さにムラがあり、
細いところでプチプチ切れる。
前途多難な予感。。。
研修の先生は、機屋さんの社長。
本日の社長のお言葉
「下ごしらえは糸巻きが仕事」
新作ストール「紫」
オンラインショップに、新作ストールを追加しました!
濃紫(縞)、薄紫(縞)、紫の濃淡のみじん格子、の3種類です。
寒い季節にぴったりの、ふんわり温かいストールです。



オンラインショップ
紬ストール販売はじめました。