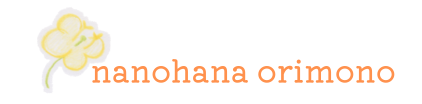3日目は、Oさんの生徒さんと結城紬の織り子経験者のMさんも加わり、
大人数、賑やかな講習会となりました。
まずは、整経が終わった経糸の糊付け作業。
小麦粉の濃度18%の液につけるのですが。
小麦粉の種類、ダマにならないような溶き方、お湯の温度、などなど。
たくさんのポイントがありました。
社長のお言葉
「経糸の糊付けが上手くいけば、下ごしらえは成功」
と言われるくらい、糊付けがポイントとのお話。
この後に続く、機巻きや機織りも、経糸の具合で作業のやりやすさが格段に違います。
糊付け後は、経糸を吊って、どんどん乾いていく糸を手早くさばきます。
人手があるほど、効率が良いです。
乾燥しているので、あっという間に乾きます。
その後は、筬通しの準備。
綾の部分を、一つ一つほぐします。
綾を崩さないよう、丁寧に作業。
指を使う作業が、とても多いです。。。
やっと、筬通し。
670箇所に、上下の経糸2本を通していきます。
これが、見えない見えない。
「から」と呼ばれる、筬目を飛ばして通さないように。
「4つ入れ」と呼ばれる、一つの筬目にダブって通すことがないように。
細心の注意を払って、通していきます。
3日目は筬通しで終了。
慣れない作業で体がカチコチ。。。